真理さんへ
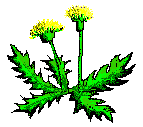 また春がめぐってきました。道端のあちこちにかわいいタンポポの花が、黄色いまん丸な笑顔をのぞかせています。私は子供たちと一緒に、あっちのタンポポ、こっちのタンポポと、順々に声をかけながら散歩する毎日です。固く冷たい地面のどこで、こんなにも小さな命が寒い冬を耐え春を待っていたのかと思うと、この世に存在する命あるすべてのものの生きる力と、それを見守る大いなる自然の厳しさと温かさを思わずにはいられません。
また春がめぐってきました。道端のあちこちにかわいいタンポポの花が、黄色いまん丸な笑顔をのぞかせています。私は子供たちと一緒に、あっちのタンポポ、こっちのタンポポと、順々に声をかけながら散歩する毎日です。固く冷たい地面のどこで、こんなにも小さな命が寒い冬を耐え春を待っていたのかと思うと、この世に存在する命あるすべてのものの生きる力と、それを見守る大いなる自然の厳しさと温かさを思わずにはいられません。
私は最近、自分の人生に貫かれた一本の見えない糸を感じさせられるような出来事に出会いました。大いなる意志の力とでも呼ぶべきもののような、その糸の存在に気づいたことは、自分がこの世に生かされているということの意味に思わず深い畏敬を抱かせられるような発見でした。私は今それを他の誰かに伝えたいと思っています。そしてそうするにはやはり、私の人生に起こった事実の流れをそのまま書いていくのが、一番いいような気がしています。そうすることによって、人間の目には互いに無関係で切れ切れにしか見えなかった一つ一つの出来事が、不思議な綾を織り成して、全体で一つの大きな物語となっていること、そしてそれが神様の描かれたストーリーであることが、自ずとわかってもらえるように思います。
|
|