![]()
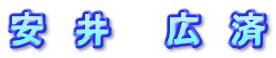
一仏教はインド、中国、日本三国にわたり、その思想の発展の様相はまこと複雑であり、多岐である。
けれども、仏教思想に一貫した基調は「何か」ということになれば、おそらく、これは、「無常」とか、「無我」とか、「空」といわれる思想にもとめられるであろう。
どのように発展し変遷した仏教であっても、いやしくも、仏数であるかぎり、すくなくとも、無常、無我、空の思想が、その基調になければならない。
仏教は、無常、無我、空の思想を基礎としておればこそ、他の宗教思想とちがった独自性をもつと考えられるのであって、もし、仏教に無常、無我、空の思想がなければ、もばや、それは仏教でないといって過言でない。
他の宗教思想によると、人間は神によってつくられたものである、ともいわれる。
しかし、仏教では超越的な神は語られない。
仏教は、無常、無我、空という、現実に対する反省よりはじまるのであって、ここに仏教的な特色がある。
はかないことを語る思想である。
無常と無我と空とは、それぞれ意味のちがった、言葉であるが、これらはいずれもままならぬ人生の道理を語り、さだめがたいこの世の姿を語る点では、同じ言葉である。
このために、仏教の無常、無我、空の思想は、人間の理想や、希望を否定する、消極的な、暗い、あきらめの人生観として、強くうけとられている。
これは、通俗の一般的理解であって、充分な正しい理解とは考えられない。
しかし、「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり……おごれるもの久しからず、ただ春の夜の夢の如し。」というような、消極的な、否定的な、はかない、むなしさの感情、これが、仏教の無常、無我、空の思想の一般的な了解であることは、ともかく否定できない。
本論稿は、このような点をかえりみて、仏教の無常、無我、空の思想がもっている、肯定的な現実的性格をさぐってみようとするものである。二
いったい、仏教によると、すべてのものが無常であり、無我であり、空であるのは、すべてのものが「因縁生」であるからである、と考えられている。
たとえば、美しい花が咲くと、われわれは、いつまでも、この花が美しく咲いていてほしいという、感情をもつ。
しかし、種子の良否、日光や水分や肥料の工合というような、内外さまぎまの困縁の事情の如何によって、花はながもちすることもあり、また、ながもちしないこともあって、いつまでも美しく咲いているわけではない。
花は、そのものを成り立たしめる因縁にしたがって生じ、したがって、因縁が変れば、色があせ、やがて散ってゆく。
花が生ずるも、滅するも、すべては因縁次第であって、花にたいするわれわれの主観的な愛着の感情は、成り立たない。
花は、われわれの心にそむく、無常な、無我な、空しい存在である。
仏教は、すべてのものが、無常であり、無我であり、空しいものであることを、このような「因縁生」(因縁滅)ということで語っている。
つまり、われわれのもつところの、花、という主観的な固執・執着の観念は、種子や日光や水分などの客観的な因縁が存在するところにありえているところのものなのであり、したがって、それらの因縁が崩壊すれば崩壊せざるをえない、無常な、無我な、空しい運命にあるのであって、ここに仏教の「因縁生」の道理の意義がある。
だから、仏教の因縁生の道理は、ぎわめて、客観主義的な考え方であるように思われる。
なぜなら、花が生ずるも滅するも、すべてが客観的な因縁次第であって、われわれの主観的な固執・執着の立場が、空しいとするならば支配力を有するものが、全く、客観的な因縁にある、といわねばならないからである。
そして、また、そのかぎり、わわれわれは、花にたいする主観的な愛着を断念し、色があせ、散る花を見て、これらを、すべて、客観の因縁のなすところと、あきらめねばならぬであろう。
われわれは、花にたいして愛着するのみならず、身体や地位や身分や、富や財などの、さまざまのものに愛着する。
しかし、因縁生の道理によるかぎり、これらの愛着が空しく、われわれが、これらすべてを因縁のなすところと、あきらめねばならないことは、これまた同様である。
身体は、因縁生の道理によるかぎり、そのものを成り立たしめる因縁である、骨や筋肉や胃や腸などの機能の調子がよければ健康であるが、それらの因縁の機能の調子がわるければ病気になり、因縁の事情の如何によっては崩れ去る、無常な、無我な、空しい存在といわねばならない。
だから、身体も、また、愛着の対象となるべきものでなく、われわれは、ただ身体を因縁にまかせて、すべてを因縁のなすところと、あきらめるよりほかはない。
地位や身分についても、また、同様である。
われわれは、自分の地位や身分にとらわれる。
しかし、地位や身分を成り立たしめている客観的な因縁の事情が変ってくると、われわれは、これらを失なわねばならなくなってくる。
地位や身分にたいするわれわれの主観的な愛着は無力であって、われわれは、ただ、すべてを因縁のなすところと、あきらめるよりほかはない。
花の身体も地位も身分も、すべては、はかなく、空しい存在であり、因縁にたいしては、ただ、あきらめあるのみである。
いかに莫大な富でも、経済の大変動があり、その富を成り立たしめている因縁の事情が一変すると、一挙にして失なわれることもある。
因縁生の道理によるかぎり、富や財の如き、まことに、はかなく、空しい存在であり、因縁にたいしては、ただ、あきらめるよりほかはない。
仏教の無常、無我、空の思想が人間の理想や希望を否定する暗いあきらめの人生観とみなされる理論的な根拠をもとめると、実に、これは、右にいうような、因縁生の道理の上にみとめられる。
もっとも、すべてが因縁生であり、すべてが客観的な因縁の事情の如何によるのであれば、常識的にいえば、だからしてむしろ、われわれは、客観の因縁の解決に向って努力すべきであり、客観の因縁にたいして消極的にあきらめるべきでないというようにも考えられる。
花が種子や水分などのさまざまの因縁によるのなら、そのかぎり、むしろ、われわれは、花がながもちするように種子の品質を改良し、日光や水分の量を適度にすればよいのであるし、身体が骨や筋肉や胃や腸などの因縁によるのなら、そのかぎり、むしろ、われわれは、身体が病気におかされないように、骨や筋肉や胃や腸などの機能の増進をはかればよい、というように考えられる。
すべてが環境の如何に支配されると考えて、環境の改善をはかろうとする唯物論的立場、あるいは、科学的立場といわれるものが、これであろう。
しかし、科学的に客観を解決する方法は、どこまでいっても、果てしがなく、これでよしとして満足するところがない。
客観の因縁は、つねに、解決しつくされずに矛盾し、客観の因縁を解決しつくそうとする人間の主観的な固執・執着は、現実において、つねに、はかなく、むなしい。われわれは、どうしても、客観に打ち勝つことができず、客観以上のものを望むことができない。
だから、結局、仏教では、客観の因縁の支配力を認め、我々人間の固執・執着の立場の無力を語るのであると思われる。
このような意味からいうと、因縁生の道理は、人間の意志や努力の限界をついた真実を語っている、といってよい。三
しかし、因縁生の道理が人間の意志や努力の限界をついた真実であるにせよ、だからといって、因縁生の道理は、はたして、暗い、あきらめの思想なのであろうか。
アビダルマ仏教によると、支配力を有するものは「法」である客観的因縁であり、「人」である自我の立場は空しいと考えられている。
アビダルマの小乗仏教にとって、実在するものは、ただ客観の因縁のみであったのであり、したがって、われわれは、すべてを因縁とあきらめ、自我の見解をさるよりほかはないと考えられたといってよい。
「人空法有」といわれる立場がこれであり、仏教では、この立場が因緑生の考え方の一つの大きな伝統となっている。
以上に述べた因縁生の道理は、むろん、この考え方であり、日本文学にしばしばあらわれる詠嘆的なあきらめの無常観は、またこの因縁生の考え方のあらわれであるといってよい。
しかし、仏教の因縁生の考え方は、大乗仏教の伝統では、非常におもむきが変っている。
大乗仏教になると、「人」である自我の立場はもちろん、「法」である客観の因縁もまた、空しいものと否定されてくる。
アビダルマ仏教では、支配力をもつものは、客観の「法」である因縁であるから、すべてを因縁にまかせで、あきらめようとする。
だから、「人」が否定されて、「法」である因縁に実在が立てられる。
ところが、大乗仏教になると、「人」が空しいものとして否定されたばあいには、同時に「法」である因縁も空しいものとして否定されねばならない、と考えられてくるのである。
これが大乗仏教の「人法二空」の立場であって、ここに、大乗仏教の因縁生の考え方の特色が見られる。
アビダルマ仏教の「人空法有」の立場では、すべてを因縁にまかせて、あきらめようとする。
しかし、大乗仏教からいえば、このあきらめは不徹底で、徹底してあきらめたばあいには、因縁は、もはや問題にならず、否定されてくるのであろう。
客観的因縁に勝てないから、あきらめるより仕方がない、という立場では、因縁というものの存在をみとめ、これに束縛され、これにいやいやながら従っている。
これが「人空法有」の立場である。
しかし、勝てないというあきらめに徹底すると、客観的因縁はもはや問題でなくなり、客観的因縁に束縛されるというようなこともなくなってくる。
客観的因縁すら否定して、これにとらわれず、わずらわされず、これに打ち勝ってゆく。
このような、人法ともに空じ否定した、ときはなたれた、束縛のない境地、これが、大乗仏教の因縁生の意味するところであろう。
したがって、大乗仏教の因縁生の考え方には、もはや、暗い、あきらめの意味はない。
ここには、むしろ、あらゆるものに束縛されない、明かるい、自由が意味されている。
ここには、あらゆるものにわずらわされず、これらとともに明るく生きてゆく、という意味がある。
元来、仏教は、科学的立場のように、客観的因縁に勝とうとしたり、さからったりして、客観的にものを解決しようとする方法をとらず、自我の立場をさることによって、実は、客観的因縁を克服しようとする、心の鍛錬の道として発達したといってよい。
自我の心をもって、客観的因縁に勝とうとしたり、さからってゆくと、客観的因縁は苦悩のたねとなってくる。
しかし、自我の心をすてて、客観的因縁にさからわず、勝とうとしないかぎり、客観的因縁に苦しめられることがない。
たとえ、どのような逆境や、都合のわるい因縁に出会っても、これにさからう自我の心がないかぎり、これらは、一向に問題にならず、これらを、そのままのみこむことができる。
どのような因縁にも苦しめられず、これらを、そのままよしとして、明かるくうけいれることができる。
仏教にいう解脱とは、本来、このような意味であろう。
解脱とは、苦悩の因縁より解放され、自由になることである。
だから、解脱とは、すべてにわずらいなく、明かるくなることでなければならない。
このような意味で、「人」である自我の立場のみならず、「法」である客観的因縁も、ともに空であるとした、大乗仏教の「人法二空」の立場は、仏教の因縁生の道理の正しい理解であるというべきである。
これに反して、客観的因縁の支配的な実在性をみとめ、すべてを客観的因縁のなすところとあきらめて、自我の見解をさろうとした、アビダルマ仏教の「人空法有」の立場は、仏教の因縁生の道理の形式的な理解というべきである。
「因縁によって生ずる」というのが、因縁生という言薬の文字どうりの形式的な意味である。
だから、因縁生という言葉には、たしかに、宿命とか、あきらめ、というような暗いひびきがある。
因縁生であるから、無常であり、無我であり、空である、という教説には、人生のさだめがたい、ままならぬ、はかなさが、因縁のなすところとあきらめるよりほかのない宿命として、たしかに示さかれている。
しかし、この教説をこのまま文字どうりに理解しては、不充分であり、その真義をえない。
この教説には、人生のすべてのものの、ざだめかたい、はかなさ、むなしさを、因縁のなすところとあきらめるほかのない宿命として、あきらかに知ることにより、かえって、すべてをそのまま如実にうけいれることが、意味されている。
因縁をそのまま如実に明かるくうけいれ、さだめがたい、はかなさ、むなしさを、そのまま如実に明るく肯定する世界が、意味されている。
「人法二空」を語る大乗仏教は、実にこの真義を開顕したのであって、ここに、仏教の正しい了解がある。
龍樹の中観の仏教では、「因縁生であるから、空である」ということは、以上に述べてきたような、人生のはかなさ、むなしさ、というような意味だけでなく、一般に、すべてのものが、無自性であり、固定的に限定して考えられないことを意味している。
だから、龍樹の中観仏教では、因縁生であるとか、空であるということは、ただに人間苦の問題にとどまらず、一般的な理論的哲学の問題となり、龍樹は、さまざまの点から、われわれのもつあらゆる概念的理解が無自性空であることを論証する。
しかし、龍樹の意図するところは、やはりどこまでも、すべてを、そのまま如実にうけとり肯定することであり、これが、かれの思想の根本的態度であったようである。
たとえば、龍樹は『廻諍論』の中で、「もし、汝の言葉にしたがって、火が自と他との二つの体を照明するならば、火の如く、闇は自と他との二つの体を覆うであろう。」(第三十六偈)といっている。
これは−火が闇を照らすとき、われわれは、光の原理、闇の原理を、概念的な立場から、独立した実体として固定的に限定して考える。
しかし、火と闇との二つの独立した実体を固定的に限定して考えては、火は「自と他との二つの体を照らすもの」、闇は「自と他との二つの体を覆うもの」として、両者はどこまでも対立するばかりであって、火が闇を照らす一つの具体的な結合の事実が考えられなくなってくる。−という意味の論破である。
だから、これをうらがえしていえば、火が闇を照らす結合の事実を考えるためには、火と闇という二つの実体を固定的に限定して考えないで、それらの二つを「相対的に縁って」成立する無自性なるものと考えなければならない、ということになる。
生によって死、死あるによって生である如く、火と闇とは、相対的な概念であり、独立自存的に固定的に限定されて成立するのではない。
われわれは、実は、火と闇とを、相対的なるままに、無自性空なるままに、いいかえれば、有自性的な観念をさって、おのずから無心に見なければならない。
ここに、火が闇を照らす事実を、その事実に即して、如実にながめる所以がある、というべきである。
実に、ここに、火が闇を照らす抽象化されない具体的な実相をながめる所以がある。
龍樹の論破をうらがえしていえば、このような意味であり、ここに、龍樹の論破の意図があったと考えられる。
だから、龍樹の空観は、すべてのものを、その本来の事実に即して如実にながめ、そのまま如実にうけとる道であり、前に述べた因縁生の思想と根本的に同じである。
龍樹では、「因縁生の道理」が「相対性の道理」として理解されるが、これは、因縁生の道理が、「人法相対」の意義をもち、「人法二空」を語る理論でなければならないことをあらわすためとみられる。
ただ、龍樹の相対性の道理では、人法の相対というにとどまらず、火や闇の如き、一般的な、あらゆる概念的理解の相対性にまで、その相対の意義がひろげられていることが、注意されるのであるが、しかし、いずれにしても、すべてのものを、その事実に即して、そのまま如実にながめることが、究極的な意義であることに、変りはない。
また、これが、仏教思想の特色であろう。四
仏教の無常、無我、空の思想は、暗い、否定的な人生観であるように見られている。
しかし、以上、考察する如く、これは全く誤った見方であって、これらの思想は、実は、はなはだ肯定的な思想である。
あらゆるもの、あらゆる出来事を、そのまま如実にながめるのが、これらの思想の要諦であって、究極において、これらの思想に、なんら暗い否定的な影はない。
人生を暗く見ず、すべてを当然とし、あたりまえとして、その事実に即して明かるく了解するところに、これらの思想の意義がある。
火が闇を照らす事実を、おのずから無心にながめるように、われわれは、分別をまじえずに、すべてを自然におのずから無心に見なければならない。
このような、現実の事実とともに無心に生きる絶対肯定的な態度に、これらの思想の究極的な実践的意義がある。
日日是好日とは、これであろう。
龍樹は『廻諍論』の中で、「我れに主張なし」(第二十九偈)といい、「我れは何物をも否定せず。」(第六十四偈)といっている。
空を主張するかぎり、空は有を否定するものとなる。
しかし、空は、有をしりぞけるために主張されるところの、相対的な否定の原理の如きものではない。
実に、龍樹にとって、空は、有が本来もっている、おのずからなる如実の相であり、この有のおのずからなる如実の相を肯定することこそ、かれの空論の目的であったのである。
有を否定せず、有を肯定し、日日の有の当相におのずからに生きること、このことをはなれて、仏教の無常、無我、空の思想は考えられない。
したがって、空は中道といわれる。
空が、有を否定する空でなく、有の如実相であるならば、有は、否定的に肯定せられ、非有非無という意味をもってくるからである。
空有の相即に中道の意味があるのであって、経典にも「空性によって諸法を空になさず、諸法こそ空なり。……かくの如き観察、これが、迦葉よ、中道にして、話法の如実なる観察といわれる。」(宝積経、迦薬品)といわれている。
色即是空、空即是色といわれるのも、また、この中道の意味である。
要するに、中道とは、現実の世界を否定せず、現実の分別をまじえずに、おのずからに、虚心に生きることであり、空観は、このような、絶対肯定的な中道的現実性をもつのである。
人生のはかないむなしさのみが観ぜられるばあいには、現実の人生は、厭わしく暗く否定されてくる。
ここに、現実逃避があり、また、自己を厭うばあいには、最後には、死があるのみである。
大乗仏教によると、小乗の声聞は現実の生死の世界を厭い、煩悩も肉体もともに死滅した無余依涅槃を最上の安楽と考える、といわれている。
しかし、大乗仏教は、空、あるいは、無常、無我の実践を、このような現世否定的な方法で考えない。
大乗仏教は、現実のは、かない生死の世界を厭わずに、これを、あるがままにあたりまえとして、虚心に如実に肯定的にうけいれるところに、空観の究極の意義を見るのであって、ここに、涅槃の理想をおいている。
「高原の陸地に蓮華を生ぜず、卑湿の淤泥に、乃ち、比の華を生ず。」(維摩経、仏道品)というような、生死即涅槃の中道の境地こそ、実に、大乗仏教の理想とする涅槃であった。
龍樹も『中論』の中で、「生死には何ら涅槃との区別はない。
涅槃には何ら生死との区別はない。」(第二十五章、第十九偈)といっている。
大乗仏教が在家仏教といわれるのは、ここに理由がある。
しかし、ここで、もうすこし、考えてみよう。
というのは−「生死の世界を厭わずに、これをあるがままにあたりまえとして、如実にうけいれる、生死即涅槃」というけれど、いったい、これは、具体的にどのようなことなのか。
ともかく、これが、現実のはかない生死の世界をあるがままに明かるくうけいれる、肯定的な強い人生態度であることは、わかる。
しかし、それにしても、この生死即涅槃が、ただこれだけのものならば、そこに、積極的な活動性がないのどはないか。−と考えられるからてある。
われわれの社会を動かしているものが、政治であり、経済であり、科学であることを思うとき、ただ現実を厭わずに明かるくあるがままにうけいれる、というのみでは、無気力のそしりをまぬがれない。
むろん、仏教は、政治や、経済や科学のような客観的な道でなく、自己の心を問題とする反省・自覚の道であるところに、宗教としての特色をもっている。
しかし、それにしても、動乱ただならぬ現実の中にあって、ただ現実を厭わずに明かるくあるがままにうけいれる、というのみでは、あまりにも受動的であり、結局、小乗仏教のような、寂静主義におちいり、諦観におちいるのではないか。
さもなくば、現実とあるがままに妥協する自由奔放の境地を生死即涅槃の如くに考える、あやまった特殊の態度にもおちいってしまう。
仏教が過去に歩んできた道をふりかえるとき、仏教の寂静主義的な諦観的傾向は、一般に、否定できないようである。
しかし、大乗仏教が語る生死即涅槃は、静かな諦観におちいるような、無気力な、消極的な意味のものでなく、真実には、きわめて積極的な活動性をもつもの、と考えられる。
なぜならば、生死の世界を厭わずに、これをあるがままにうけいれるところに、生死即涅槃の意義があるかぎり、生死即涅槃の本質は、生死の世界を愛する「慈悲」というべきであるが、そのかぎり、生死即涅槃の内容は、あくまで、生死の世界に積極的にはたらきかけるものでなければならないからである。
生死の世界を愛するかぎり、病を見ては薬をほどこし、貧苦を見ては財をほどこすというような、憐愍・同情の行為や、過失があれば正すというような、破邪の行為も、生死即涅槃にはあるはずである。
たとえば、『維摩経』に「劫中に疾疫あれば、現じて諸の薬草となり、若し之を服する者あれば、病を除き衆毒を消す。
劫中に饑饉あれば、身を現じて飲食となり……劫中に刀兵あれば、之れが為に慈悲を起して、彼の諸の衆生を化して、無諍地に住せしむ。」(仏道品八)と説いているのは、この意味であろう。
要するに、生死即涅槃は、たんに、生死の世界をあるがままに明るくうけいれるという、ただそれだけの観想的な意味のものでなく、これには、慈悲の心にうらづけられた、なすべきをなし、主張すべきを主張する、積極的な実践をともなうと考えられる。
だから、もし、われわれが、深く生死の世界を愛する慈悲の心からなすべきをなし、主張すべきを主張するならば、ここに、生死即涅槃の意義があるといってよい。
なすべきをなし、主張すべきを主張する、能動的実践は、そのときの事情にしたがい、われわれのよしとする判断にしたがって、実践されるのであって、こまかくいえば千差万別である。
経典によると、「或いは現じて婬女と作り、諸の好色の者を引くに、先ず、欲の鈎を以てひいて、後に仏智に入らしむ。」(維摩経、仏道品第八)ともいわれる。
しかし、ともかく、われわれが、生死の世界をあるがままにうけいれる慈悲の心にもよおされ、自分が適切と考える判断にしたがって、なすべきをなし、主張すべきを主張するならば、ここに、生死即涅槃の意義があるといってよい。
或いは、現実の社会生活においては、さまざまの主義があり、主張があり、立場がある。
右派があり、左派があり、中間派があって、みずからのよしとする主張は、人によって異なっている。
しかし、どのような立場にあっても、深く社会を愛する心から、とらわれをはなれ、私利私欲をさって、虚心にこれらの主義や主張がなされるならば、むろん、このような所にも、生死即涅槃があると考えられる。
非有非無の中道というのは、まさに、このような姿であろう。
仏教の中道は、一般にいう、あれとこれとの真中とか、いずれにもかたよらずほどほどであるとか、中をとって妥協する、というような意味とは、大いにちがっている。
仏教の中道は、中間派の態度を意味しない。
仏教の中道は、右派にも左派にも中間派にも、どのような立場にもありうるところの生死即涅槃の姿である。
自我の無反省な肯定(有)におちいらず、自我の消極的な否定(無)におちいらず、慈悲の心をもって積極的に社会に実践的に生きること、ここに、仏教の中道の意義がある。
仏教は、このような意味において、現実の社会生活とともに生き、政治や経済や科学とともに生きていくところの、真実に現実的な道といえよう。
(本稿は、拙著「中観思想の研究」に発表した縁起説の教理史的考察にもとづきながら、日頃の自分の理解を率直に述べたものである。資料の考証や研究についての詳細は、「中観思想の研究」を参見していただきたい。)
![]()