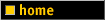醸界春秋No.49(82-83P,1998年4月)
【大人の飲みもの】
わんぱく盛りの2人の息子相手にドタバタの毎日をおくっている私のもとに、ある日突然本誌より原稿執筆依頼が舞い込んだ。このようなお酒の専門誌があることすら知らずにいた上、お酒の愛好家でも何でもない。それどころか、昨年私は、アルコール依存症の父のもとで育った少女の悲しみと、希望ある生き方への再生をテーマにした童話『涙がくれたおくりもの』を書き、それが両親の手により自費出版されるという経緯があった。童話の主人公めぐは、他ならぬ小学校時代の私であり、父の酒害に20年以上も苦しんできたから、お酒にいい印象などあるはずがない。そんな私に原稿依頼だなんて、何かの間違いだ、と正直思った。でも、よくよく読むと「酒は酔うためのものではなく、嗜むべきもの」をモットーに、滴量飲酒運転の推進を目的として発行されている、とのこと。それならこっちも、思うことを率直に書いてみようと思う。
お酒の印象を書こうとすると、私の場合、どうしても飲み方に対する印象とオーバーラップしてしまう。どこそこの銘柄がおいしいとか、まずいとか、まろやかだ、こくがある、渋い、云々ーというよりも、楽しいお酒、静かなお酒、どんちゃんやるお酒、ウサをはらすお酒、たちの悪いお酒、荒れ狂うお酒----という風に、飲む人の姿、飲み方、果てはそこに繰り広げられる人間模様まで、どうしても思い浮かべずにはいられない。
正直なところ、私には父のお酒の飲み方が嫌いであった。童話にも書いたが、それは「三度の飯よりも酒」、いや、起きがけの一杯のウイスキーから始まる「飯抜きの酒」であった。そして、機嫌のいいうちは相手にも杯を強要する強引な酒であり、やがてはつかみあいの喧嘩に変わる凶暴な酒でもあった。酔った父にいつも殴られ、ぼろぼろになっている母を見ていたから、お酒とは人を狂人へと駆りたてるもの、というイメージしかなかった。子供心にも、この世から何か1つのものを取り去れるなら、お酒をなくしてしまいたい、とさえ思っていた。
そんな私もやがて大人になると、いろいろな人のいろいろな飲み方、またお酒との付き合い方があることを知った。お酒を効用ある範囲にとどめて上手に利用できている人たちのいることも知った。かなりの酒量ながらも、情緒の安定した、信頼のおける飲み方をしている人を身近にも見てきた。私自身、一口のワインで料理が引き立つのを感じながら、食事を味わうこともある。
が、しかし、である。アルコール依存症という、自己も周囲をも破壊してしまう恐ろしい病気が存在するーしかもおびただしい数でーのも事実である。今回私の童話に関する新聞記事が出たことにより、全国の酒害に悩む方々から、涙なしには読めない手紙を多数頂いた。家族を地獄のどん底に突き落としてまで、何が楽しくて飲み続けているのだろうか。私も父に対して、こんなにまで母と私を苦しめてもお酒をやめれないなんて愛情のひとかけらもないのかと、かなり憎んだ。しかしずっと後になって、アルコール依存症という病気のことを知るようになると、アルコールには、限度を超えた飲み方を繰り返した場合、もはや身体がアルコールなしではやっていけなくなる中毒性があるということがわかってきた。お酒がきれてくると、禁断症状というのが出るらしい。脳も破壊されているから、正常な思考だってできない。飲んでいる本人も、もはやお酒の味わいを楽しんでいるわけでもなく、悪循環の中で飲み続けているだけなのである。そうしたアルコールの恐ろしさというものは、早いうちからもっと認識されるべきではないだろうか。
最近グルメ志向からくるワインブームだったり、果汁入り炭酸飲料と間違えそうな軽い感覚のお酒があったりで(実際先日もイベント会場で、ジュースと思ってもらってきたものが口にしてみて初めてお酒とわかりびっくりした!)。お酒に対する若い世代の印象も、おしゃれ感覚で楽しめる身近なものになってきているような気がする。だが、お酒を飲むということは、やはりジュースなどを飲むのとは一線を画した、重みのあるものであってほしい。そういう慎重さがないと、アルコール依存症やイッキ飲みによる死亡事件のような悲劇は後を断たないのではなかろうか。
私は主人の仕事の関係でアメリカに住んだ経験があるが、お店でお酒を買おうとすると、日本人が童顔に見えるせいか、30才を過ぎていても尚、身分証明書の提示を求められることが何度となくあり、「また若く見られたね!」と冗談で喜び合ったものである。そのくらいお酒は、きちんと分別をわきまえた大人が、その魅力も害もわかった上で、手にできるものであってほしい。そして、精神的に”熟成された”大人だけが味わえる飲み物であってほしい。